生きている人の光を写す、ナムフォト「Yei!〜楽しい遺影」〜影は光で、死も光だったお話/楢侑子さん vol.2
2017.03.14
「まいてら」のみなさま、こんにちは。ナムフォトの楢侑子です。
大阪市中央区・天満橋にある小さな写真スタジオ「ナムフォト」を営んでおり、「いかに生き、いかに逝くか 写真を通して考えよう」というコンセプトで、撮影やワークショップを行っています。
なぜ、ナムフォトを始めようと思ったのか?そんな経緯をお話した第1回目に続いて、今回はナムフォトの具体的なプログラムについてご紹介しようと思っているのですが、その前に、私自身が「生きること」や「死ぬこと」をどうとらえてきたのか、なぜ今写真を撮っているのか、また「遺影(写真)」をどんな風にとらえているのかなどを、併せてお伝えしてみようと思います。
「死」は「自然の摂理」か「不条理な出来事」か。

さて、突然ですが質問です。あなたがこの世に生まれてきて、初めて「死を体験した」のはいつだったでしょうか?また、どんな気持ちになったでしょうか?
「初めて死を体験した」と感じるとき、多くの人は、家族や大切な誰か、または家族の一員のようなペットを亡くすのが一般的なのかな?と思います。また、その時の気持ちには“哀しみ成分”が多いのかな?と想像したりも。
この世に生まれてきたものの未来には、必ず「死」があると考えると、まさに「死」は自然の摂理。お腹が空く、食べる、寝る、出すといった営みの横並びにあっても良さそうなものなのに、なかなかそうは思えません。
私が生まれて初めて「死」と対面したのは、 19歳のとき。50代半ばの恩師を亡くした経験でした。
「生きていた人が、この世から消えてしまい、二度と会えなくなる」
今より若かった当時は、そんな当たり前の事実が「自然の摂理」というよりかは「不条理な出来事」のように感じられていました。
一番信頼していた、大人の死

子供が大人へと成長していくとき。経験が不足している子供が、精神的に、肉体的に、そして社会的に自立するためには、大人の援助が必要です。人間社会では親や先生が「育児」や「教育」などの名目のもと、自立への道を手伝うシステムになっています。
私も、たくさんの方の助けや教えをいただき、これまで生きてくることができました。今ではとても大きな感謝を感じていますが、子供時代には、なかなかプラスの感情を持つことが難しい時期もありました。
そんな子供時代の私が心の拠り所にしていたのが、塾でした。大好きな先生が居たのです。
私が興味を持っていること、テストの結果(良し悪しに関係なく)、進学について、デザインやアートの世界など、すべてを尊重し、私の将来を応援してくれました。先生から見て「間違っている」と思ったことも、きちんと教えてくれました。
一緒に美術館へ行ったり、本を貸してくれたり、クラス以外でも何かと仲良しだった先生。いつだったかアートの話をしていたときに、先生は「いつか、スペインに滞在して、毎日絵を描いて過ごすのが夢だ」と話してくれました。
私は「なんで、今すぐ行かないんですか?」と尋ねると、先生は「今は、絵を描いたり、作品を作っているわけではないけど、人を作っているでしょ?教育とはそういうものだと思っているよ」と、とても満足そうにおっしゃったのです。

教えてもらったのは、英語だけではなく。
「私は、本当にやりたい事を目指してもいい。がんばる力がある。例え失敗してもいい」ということや、「どこにいても、光の方を向いていればいい」そんなことだったかもしれません。
先生は、私だけではなく、教え子みんなにそんな風に思わせてくれる存在だったと思います。


この素晴らしい師の、死の知らせが届いたとき。
当時私は、東京の美術大学へ通っていましたが、環八をゴーゴーと走る車のヘッドライトの光を浴びながら「これから、一体誰に報告すればいいのだろう?」と、途方もない気持ちに襲われました。
本来の寿命よりちょっぴり早い先生の死。原因は、癌でした。
「先生は、最期に“死”を教えてくれたんだなぁ」と思い、遠くからシャッターを切りました。

さらに、学びは続いていきます。
1年半後に知った、先輩の死
社会へ出てから。私は仕事をするのが好きでした。自分のイメージやアイデアを形にして、社会と繋がりが生まれて、お金がもらえる。周りのみんなも「より良くしよう」と頑張っている。そんな大好きだったITのベンチャー企業で、求人広告のWEBサービスの制作部として一緒に頑張っていたひとりの先輩がいました。
やがて、私はその会社を辞めて別の道へ進むことを選びますが、その時にも心の底から応援してくれた先輩が、 30歳で亡くなりました。
そして、その先輩の死を、1年半程が経ったとあるおめでたい席で、たまたま知ることになるのです。
電話帳に入ったままの電話番号や、繋がったままのSNS。
会わずとも「同じ空の下にいる」と思っていた先輩が、1年半前にこの世から居なくなっていた事実を目の当たりにして。
とてつもなく、空虚な気持ちに襲われ、いろいろな思いが交錯したままに、文字通り3日間を泣いて過ごしました。

先輩が亡くなった原因は、癌でした。
平均寿命よりも早い死が、より哀しく感じられるのは人間のエゴでしょうか。
今なら、少し、そう思えます。
自ら命を絶った、叔父の死
不治の病で亡くなる人もいれば、自死を選ぶ人もいる。叔父が、そうでした。
叔父の死について、みんなが色んなことを話していましたが「どうにかして、止めることは出来なかったのか」という後悔と哀しみがその多くだったように記憶しています。
死んでしまったけど、心の中に存在したままの叔父。当の叔父は、生きることよりも、死の先に、光を見たのかなぁと、今は感じています。

誰にも死の経験はやってくる。
それにしても、19歳〜20代に起きたこれらの「死」の経験。受け入れるには、それなりの時間がかかり、気付いたら「人に出逢うこと」を、そのまま等しく「いつかくる別れ」や「寂しい・哀しい・辛い」といった感情と結びつけるようになっていました。
とにかく、なるべく人と新しく出逢わないように、また人と親しくなったり、深い関係にならないように気をつけながら、過ごすようになるのです。
ただ、淡々と日々を送る。
起きて、会社へ行って、求められている仕事をして、帰ってきて、ご飯を作って、眠る。それなりに、生きていることができました。

例えるならば、毎日、毎日、曇り空が続いているようなイメージです。
雨の日は来ないかわりに、晴れの日も来ない。
気づいたら、私は、写真を撮らなくなっていました。
そして、再び撮りだした写真は、なぜだかやっぱり「人」だったのです。
光の方を向いたときに撮りだした、人の写真
私は、「30歳で編集長になる」のが夢だったのですが、それには、大学3年生のときに初めてカメラマンとして仕事をしていた経験が大きく影響しています。当時、仕事でストリートスナップを撮っていたのですが、写真を気に入ってもらい、新雑誌を創刊するプロジェクトに誘われたのです。
ところが、その雑誌は、半分ほど出来上がったところで会社が倒産。
「i」という雑誌名で、日本人を色々な切り口で取材していました。「マイノリティを持った人々」という企画で、車椅子バスケットプレーヤーの取材をしたり、「日本の匠」という企画で、花火師さんを取材したり。
「その雑誌を、どうしたら自分の手で創刊できるのだろう?」という目的意識を持ってITや雑誌、ラジオ、モバイルなど、色々なメディアで企画・編集・ディレクションといった仕事をするようになっていたのです。
ですが、東京でメディアの仕事をするとなると、「広告づくり」に行き着きます。華やかな企画の編集やディレクションをする機会にも恵まれ、それはそれで楽しいものでしたが、大量生産・大量消費の時代はもう終わり。「何かを宣伝する」ためではなく「ふつうの人の暮らしや、生活に根ざした情報発信がしたい」と思い、とにかくやりだしたのが「i〜ストリートスナップでつづる、幸せなメディア」です。
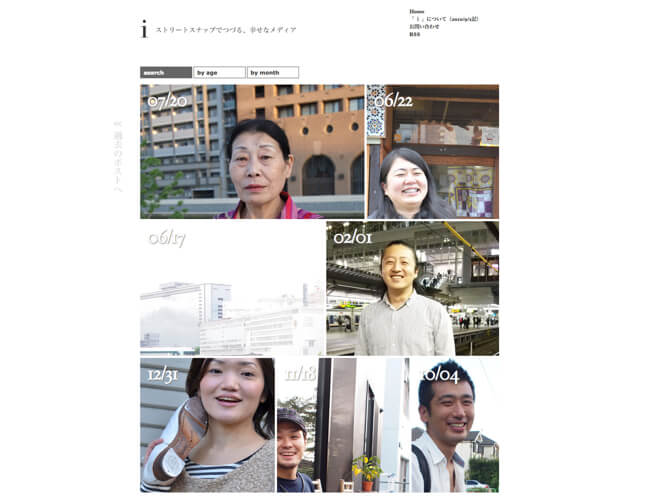
Blogを立ち上げ、街へ出て、ふつうの人に声をかけて、質問をしたりインタビューをして、更新をする。
有名人ではなく「ふつうの人の生き様にスポットライトを当てたい」という想いがそうさせました。
「ナムフォト」でやろうとしていることと、当時やっていたことの根底にあるものがまったく一緒で、今、またこの続きを歩みだしているのだと感じています。
光とまったく同じ存在の、影。
写真に写るのは、「今」という瞬間と「光」であることを、第一回目の記事でご紹介しました。
私はポートレート(肖像写真)を撮るときに、「その人の光」を写したいのです。
そして、「光」を語る上で、切っても切れない「影」という存在。ふたつは同様であることを、今再び強く感じています。

一番最初に「光」と「影」が同じものだと認識したのは、美大受験専門のアトリエでデッサンをしていた時です。
画用紙の上の静物画。机にうっすら落ちる影を丁寧に描き込まないと、「光が当たっている」ことも、そもそも「物体がそこにある」ことも表現できないのです。
もしくは、真夏の海岸をイメージしてみると、脳裏に浮かぶのは、砂浜と照り返す太陽の強い光です。一方で、砂浜に落ちる影というのは、ひときわ濃くて深くて、暗いものです。
光が強ければ、強いほど、そこへ立体感や存在感をもたらす影は、濃くて深くて、暗いものになる。
まったく同じ、光と、影。
影はそのまま光になる。光の後ろでは、影がしっかりと輝きを支えている。

影の方を見つめながら生きていることもできるのですが、あまり楽しくありません。人生は一瞬の連続。それならば、まずは「一瞬」を写す、写真から。しっかりと、ご自身の光を感じて「これが本当の私」にしてしまいましょう。


ナムフォトの「Yei〜楽しい遺影フォト」
ナムフォトでは、写真を撮る時に、あなたの人生に降り注いでいるスポットライトを受け取っていただけるよう、カメラを向けさせていただきます。
また、撮影前に心の整理をして、あなた自身が心の底から自分の光を感じていられるように、内面を整えるカウンセリングワークを提案しています。
カウンセリングワークでは、まず初めに、これまでの人生を、カウンセリングシートに書かれてある質問に答えながら振り返っていただきます。
同じ経験は「光」と「影」の見方ができると思いますが、「影」はそのままあなた自身の「光」となること。そこを認識していただき、その上であなたの人生の根底を流れるテーマや、叶えたいこと、譲れないこと、大切にしたいことやあり方、場合によっては具体的な目標を探して、言葉で表現していきます。(人生作文を完成させて、キャッチコピーを付けます)
写真だけのメニューや、インタビュー付きのメニューなどもご用意しておりますので、興味を持っていただけた方は、ぜひHPをご覧ください。
生きている間に、あなたが放っている光を写しとること。それが、ナムフォトの「Yei!〜楽しい遺影フォト」(http://numphoto.com/program/yei/)というプログラムです。
「遺影」というと、「死」を連想させたり、お年寄りのものだというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、50年か、100年も経てば、ほとんどの人は、逝きます。ということは、50年後か100年後には、どんな写真も「遺影」に。
そういう意味で、マタニティも、ブライダルも、七五三も、成人式も、なんでもないときのプロフィール写真も。すべての写真を「Yei!〜楽しい遺影フォト」というプログラムでお受けいたします。

光の方を向き、誰かを受け入れたときに起こる素敵な笑顔
実際に写真を撮らせていただいたときに
「あぁ、私、こんな顔で笑っているんですね!」
「思ってたより、私、ずっと素敵でした!」
などと言っていただけると、良かったなと思います。
人間には、目がついていて、世界の素晴らしい物や風景などを見ることができます。ですが、一生見ることができないものがあって、それが「自分の顔」です。ヒトを創造した偉大な存在(具体的な命名は避けます)は、「人は、自分の顔を見る必要がない」と判断されたのかもしれないなぁと。
あなたは、普段、とても素敵な笑顔をしていると思います。その笑顔は、誰かと接して嬉しい気持ちになったときに起こること。だから、あなたの周りの人は、あなたがどんな風に素敵に笑うかをよく知っていると思うし、あなたの笑顔をたくさん受け取っていると思います。

生きていれば、色々な感情の起伏があり、嬉しいものだけではありません。ですが、こういった感情の起伏は、いつだって誰かとの間で起こるもの。
自分の中に留まることをやめて、外へ目を向けたとき。人と関わることや、誰かがいてくれることに光を感じたときに、生き生きとした表情が生まれるのでしょうね。

今より少し前。
あんなに、辛くて寂しくて、哀しく感じていた「死」。私もあの時を抜け、今では「死」そのものの捉え方も大きく変わりました。
生きていることよりも、あの世の方に「光」を感じられたときに、そっちの方向へ進むこと。それが本来の「死」であり「逝く」ということなのかなと思っています。
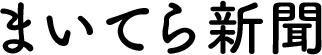

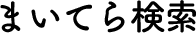

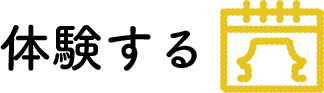
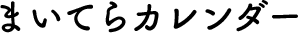
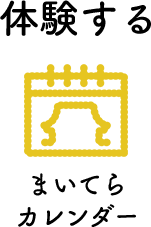

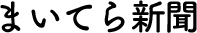

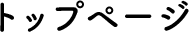
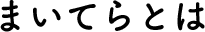
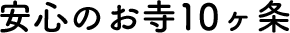
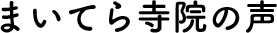
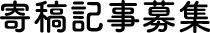
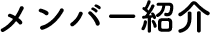
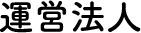



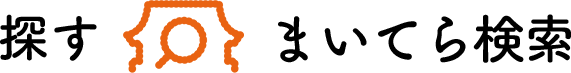

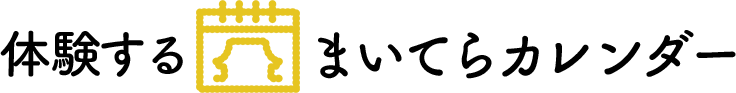
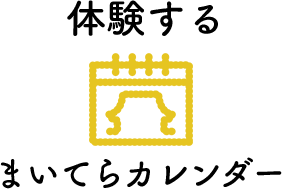
 まいてらだより
まいてらだより