想いを伝えるということ(妙華寺住職・中川和則)
2024.06.04
自分の想いを相手に伝えるって、とても難しいですよね。
片想いの告白、職場の人間関係、新商品のプレゼン、政治家の有権者への訴えなど、だれもが伝えたい想いを持ちながらも、なかなか相手に理解してもらえないものです。
お坊さんの役割は仏法を伝えることですが、妙華寺の中川和則住職(三重県・真宗高田派)も、「仏さまのみ教えをお檀家さんや地域の方々に届けられているか」と、日々、自問自答しています。
どうして人は想いを相手に伝えたいのか。どうすれば想いは相手に届くのか。中川さんの内省の中に、そのヒントがあるかもしれません。

中川和則(なかがわわそく)
1956年生まれ 龍谷大学経済学部卒 津市役所に10年勤務(医療・保険・失業対策関係の事務) その後高田本山専修寺御影堂平成大修理事務局に7年勤務 2006年住職拝命
変わる世の中。お寺に何ができるか
仏法とは、生きる意味そのものであり、わたしたちの心のよりどころになってくれるものです。この仏法を、わたしなりに日々一生懸命伝えようとするのですが、力不足を感じることも少なくありません。
私はお寺で生まれ育ち、現在68歳です。時代の移り変わりとともに、お寺を巡る環境も変化しています。核家族化や個人化により、地域のつながりも希薄になりつつあり、かつては親子三世代でのお参りも当たり前でしたが、いまは昔に比べると、お参りの方も減っています。それは、仏法を伝える場面が減っていることを意味します。
環境が変化する中でお寺として何ができるか。妙華寺では、貧困に苦しむ子どもたちにお供え物をおすそわけする「おてらおやつクラブ」や、障がいのある子、引きこもりの子やそのご家族を支援する「お寺と教会の親なきあと相談室」などに取り組んでいます。
このような支援活動を通じて、地域や家族に貢献できればと思いますし、やっぱりその奥には「仏法に触れてほしい」「仏縁を結んでほしい」という僧侶としての願いを込めています。

自ら命を絶たれたお檀家さんへ
僧侶として伝えることの難しさを考える時に、ある忘れがたい出来事が蘇ります。
副住職だった頃、とあるお檀家の息子さんがお寺を訪ねてきて「死にたい」と訴えてこられました。当時住職だった父とわたしは「そんなことはすべきでない」と彼を説得したのですが、その一週間後、その方は自ら命を絶たれました。
僧侶としてこれほどショックなことはありません。救いを求めてお寺に来られたはずなのにと思うと、悔やんでも悔やみきれません。
「彼に何を伝えたらよかったのだろうか」
ずっと悩み続けてきたこの問いに、いまのわたしならこう答えます。
「何かを伝える前に、まずはじっくりと耳を傾け、話を聴くべきだったのでは」
なぜなら、わたしたちの説得が、彼の想いの否定につながったのではと思うからです。彼には彼なりの、伝えたい想い、聴いてもらいたい想いがあったのではないか。きっと彼も、想いが伝わらないこと、聴いてもらえないことに、苦しんでいたと思うのです。
聴くことと、伝えることと
伝えることだけでなく、「聴く」こともまた難しいものです。私は傾聴について学び続けていますが、相手に想いを出し切ってもらうこと、それをこちらが心から受け止めることの難しさを、日々感じています。
でも、こちらが真剣に耳を傾けると、相手も嬉しそうな表情をします。話す側と聴く側の、お互いの想いが通じ合った時、心が癒され、救われる気分がします。
人が「伝えたい」と願うのは、きっと相手に自分のことを知ってもらい、共感や共鳴がほしいからなのでしょう。共感や共鳴は人間が望むもっとも根源的な欲求の一つだと思います。
想いが伝わらないことに苦しんでいる時は、まずは相手の声に耳を傾けてみるのが一つの糸口になるのかもしれません。
同じ時間を過ごすことで伝わること
お檀家さんとの関係というのは不思議なもので、家族、親戚、友人とは異なるものの、ゆるやかなつながりが何十年と続きます。
常にしっかりとした対話ができるわけではありませんが、無理に「聴く」「伝える」という関係を築かなくても、まずは「一緒にいる」だけでいいのかもしれないと思わされる出来事がありました。
自死で息子さんを亡くされた別のお檀家さん。葬儀や法事の席であまりに辛い表情をされていると、僧侶とはいえ、ひとりの人間として言葉を失います。深く話を聴くことも、仏さまのみ教えをお伝えすることも、なかなかできずにいました。
でも、年回忌の法事を重ねるごとに少しずつ落ち着かれた表情に変化され、毎年行われるお寺の法要にも欠かさずお参りをし続けてくださいます。悲しみが癒えることはなくても、きっと長い時間をかけて、少しずつ、息子さんの死を受け入れられているのかもしれません。
深い対話ができなくても、同じ時間をともに過ごす中で、自然と心に仏法がしみ込んでいく、そういう伝わり方だってあるのでしょう。

僧侶として、そしてひとりの人間として、わたしはこれからもお檀家さんと心を通わせる努力を続けます。無理に聴こう、無理に伝えようとせずに、まずはお互いの理解を深めるために、ともに同じ時間を過ごせるお寺の運営に努めていきたいと思います。
法事や法要、地域貢献の取り組みなど、お寺で過ごす時間の中で、ひとりでも多くの方が仏法にふれるきっかけを感じ取ってもらうことを願っています。

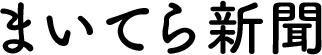

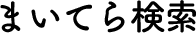

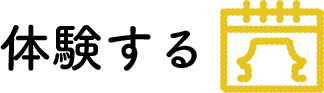
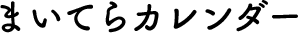
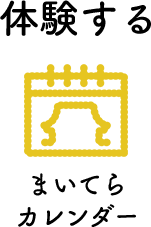

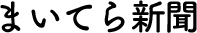

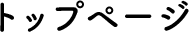
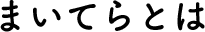
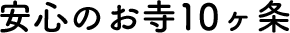
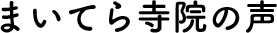
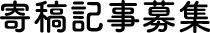
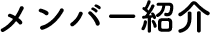
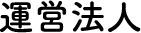



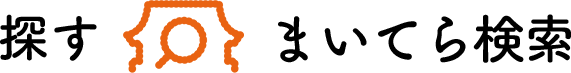

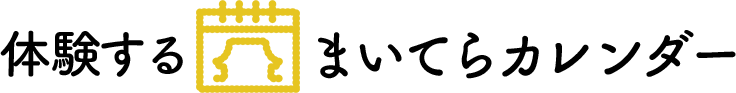
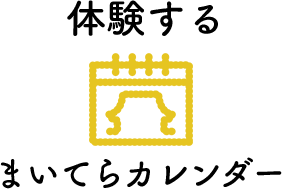
 まいてらだより
まいてらだより