法事を重ねる中で見えること。息子の十三回忌を終えて(井出悦郎)
2025.07.14
まいてら編集部の井出悦郎は、息子さんの十三回忌を営んだ際、法事の前後のプロセスを通じて色々な気づきに出会えたそうです。
現代において法事の価値を見つめ直す、「法事のすゝめ」とも言える記事かもしれません。ぜひご一読ください。
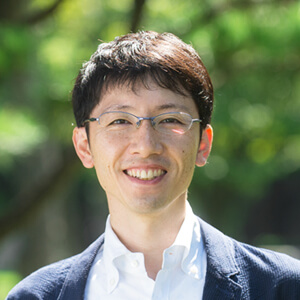
井出悦郎(いでえつろう)
1979年生まれ。人間形成に資する思想・哲学に関心があり、大学では中国哲学を専攻。銀行、ITベンチャー、経営コンサルティングを経て、「これからの人づくりのヒント」と直感した仏教との出会いを機縁に、まいてらを運営する一般社団法人お寺の未来を創業。同社代表理事を務める。東京大学文学部卒。
著書に『これからの供養のかたち』(祥伝社新書)
法事は関係性の再起動。故人が家族の関係性に息吹を吹き込む
先日、生後2ヶ月で亡くなった長男の十三回忌を執り行いました。
葬儀、四十九日忌、一周忌、三回忌、七回忌を経て、十三回忌ともなると、法事をどこまで続けるのか、家族・親戚にもどのように声をかけるのかと、正直迷うところもありました。
私と妻双方の実家に呼び掛けたところ、両家の両親、兄弟たちは快い二つ返事。あっさり快諾してくれたことにうれしさを覚えました。
例えばお正月など、各家それぞれで集まることはあっても、両家全員が一緒に集まるのはなかなかないもの。そして、両家全員がわざわざ集まるもっともらしい理由を考えることは意外と大変です。しかし、法事は両家が集まる理由をあっさり提供してくれるのだと気づかされました。
法要の際、子どもたちが一生懸命にお経を読もうとしたり、大人たちの真似をして焼香する姿に成長を感じました。
法事後の会食では、子どもたちはポケモンカードで遊んだり、走り回ってかくれんぼ、大人は会話に熱中し、それぞれが思い思いに時間を過ごしていました。その光景を見て、「今日は法事をやって良かったなぁ」としみじみ感じました。


故人を中心に置く法事は、家族・親戚の「関係性を再起動」させる力があり、供養は故人のためだけでなく、実は“遺された人たちのため”でもあるのだと再認識させられました。死してなお、家族の関係性に息吹を吹き込み続ける息子の存在は大きなものがあると、親としてうれしく思います。
法事を準備する過程で、妻と激動の日々を振り返る
十三回忌に向けた準備をする中、妻と12年間を振返りながら、当時の激動の日々、12年を経ての家族や人生の変化について色々と話しました。
妻は時々、「当時の記憶があまりない」と言います。その言葉を聞くたびに、お腹を痛めて生んだ、生後間もない我が子を亡くすことの母親のショックは相当なものだと感じさせられてきました。
ただ、年数を重ねる中で妻の悲しみも変化したのでしょう。近年は当時のかすかで断片的な記憶を自分なりに整理するかのように、言葉をつむぎ出しながら語ってくれます。少しずつ語ることで、妻なりに息子の存在を、自分の人生と家族の大切な物語に昇華させているのだと感じます。
私自身を振り返ると、当時は「私が倒れたら家族はおしまい」と、始終気を張りつめていました。主治医の先生から息子の厳しい状況を伝えられる日々の中、「お父さん、とても冷静ですね」と驚かれたこともあります。
思えば当時の私は、事実を見つめることと、事実についてどのように思うかという感情を一生懸命分離していました。事実と感情が混ざり合ってしまった瞬間に、自分が壊れ、それは即座に家族が壊れていくことにつながるという強い直感があったのです。鉄仮面のような冷静さをまとうことは、私なりに自分と家族を守るための防衛本能だったのだと感じます。
ただ、そんな私でも、とてもつらいことがありました。当時は街で楽しそうにしている他のご家族の様子が非常にカラフルでキラキラとまぶしく映り、そのような場面に出会うたびに目を伏せたり、歩く道を変えたり、近くの建物に駆け込んだり、まぶしさによって心が火傷しないよう、ダメージを必死に避けていました。
当時の私たち家族の日々はカラフルさとは隔絶し、休日は家にこもってばかり。あえて色に例えれば、当時は毎日をモノクロの記憶とすることで感覚を麻痺させ、自分たちの心を防衛するような日々でした。
法事は人生や関係性を振り返る、家族による集団的リフレクション
人生には色々な単位の時間が巡ります。一日、一ヶ月、一年という客観的な時間の流れもあれば、入学・卒業・就職等のライフステージという、人生の成長を意味づける段階的な時間の流れもあります。
昨今は社会の変化が加速する中、目の前の仕事や予定に忙殺され、長期的な視点で物事を見ることが難しくなっています。現代人は物事の見方がおのずと短期化していると言えるでしょう。
一方、法事は●回忌という形で、時間を強制的に長い間隔で切り取ります。しかも、三回忌以降は4年と6年の繰り返しという絶妙な時間で回忌がめぐってきます。
今回の十三回忌に参列した家族・親戚みんなと、しみじみ12年前を振り返るということはしませんでしたが、それぞれに「あれから12年かぁ」と去来する気持ちはあったのではと思います。
12年という歳月の中で新しい命も誕生し、子どもたちも大きくなりました。家族・親戚みんなで人生や関係性を振り返る集団的リフレクション(内省)の機会でもあるということが、法事の意義の一つだと感じます。
振返りを通じて、私たち家族にとっても、モノクロの記憶は、時の流れとともに色彩を取り戻し始めています。息子が“いない”ことを嘆き悲しむのではなく、息子が“いてくれた”ことに感謝する、温かい記憶に変化していると感じます。
私たちは故人から案じられている存在
法要当日、住職は「日々の忙しさの中で故人と丁寧に向き合う時間はなかなか取れないものですが、ご家族みなさんが今日のようにお集まりになり、故人に向き合われる時間を持たれることそのものが尊いことだと思います」と優しく語られた後、「啐啄同時」という法話をしてくださいました。
この言葉は、特に禅宗で語られますが、鳥の雛が卵の中から殻を破ろうとつつく(=啐)際、親鳥も外から殻を破る(=啄)タイミングがぴったり合うことで、無事に雛が生まれてくる様子を表します。その意味が転じて、仏教で言えば弟子が悟りや教えを求めるタイミングに師匠が適切な言動で導くことを指し、日常の中では親と子や、上司と部下などの関係にも援用されます。
供養で言えば、故人は仏様に見立てられ、師匠や親に当たります。そして、法事等に参列する私たちが弟子や子であると言えます。
法事に参列する私たちが故人に思いを致す時、その時々の境遇によって故人との関係性からつむがれる意味は変わっていきます。亡くなってすぐは悲しみが大きいですが、時間の経過とともに悲しみがやわらぎ、故人との記憶や思い出を振り返る心の余裕もできてきます。故人が亡くなった事実は変わりませんが、時の流れとともに喪失を生き直すことで、故人について語るエピソードや感じ方は、遺された人の心の成長や環境変化によって変わり続けます。
つまり、「故人をどう語るか」は自分が今どこにいるかを映す、定点観測の鏡でもあると言えます。「啐啄同時」の点から言えば、故人に思いを致す一人ひとりが、その時にふさわしい気づきを得ることでもあります。
住職は「故人を案じている私たちが、実は故人からも案じられている」ともおっしゃられ、仏となった故人と遺された家族が相互互恵的な関係を育み続けることが法事等の供養の意義と言えるかもしれません。

法事は続けることに意味がある。重ねることで見える世界がある
法事を短い回忌で終えたり、法事をしなかったりする人が増えていると言われる現代ですが、故人とともに人生を歩むことで得られる気づきは、急速に変化する時代において貴重なものだと思います。
法事は続けることに意義がある。
法事を重ねることで見える世界がある。
私はこのように思います。タイパ、コスパ等、刹那的かつ矮小化された視点で供養の是非が判断される現代において、法事の意義や役割は今こそ再評価されるべきだと考えます。
みなさんにとって、法事はどのような時間でしょうか?
故人を偲ぶ時間の意味をご自身なりに受け止めることは、人生に豊かさを添えるきっかけになるかもしれません。
ただ、家族のカタチも多様化する中で、法事をしたくてもできないという方もいらっしゃるでしょう。そのような方は、ぜひ信頼できるお寺に相談してみてください。良心的なお寺であれば、その時々の家族の状況に合わせた最適なカタチを提案してくれると思います。
息子の十三回忌はその前後のプロセスを通じて、色々な気づきをもたらしてくれました。私たち家族なりのかたちで、これからも法事を重ねていきたいと思います。感謝。
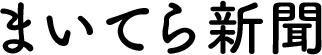

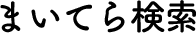

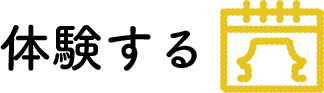
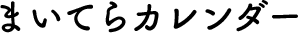
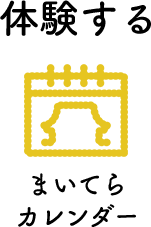

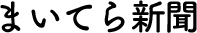

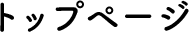
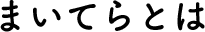
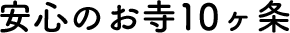
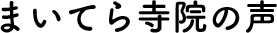
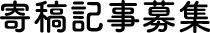
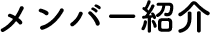
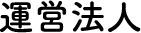
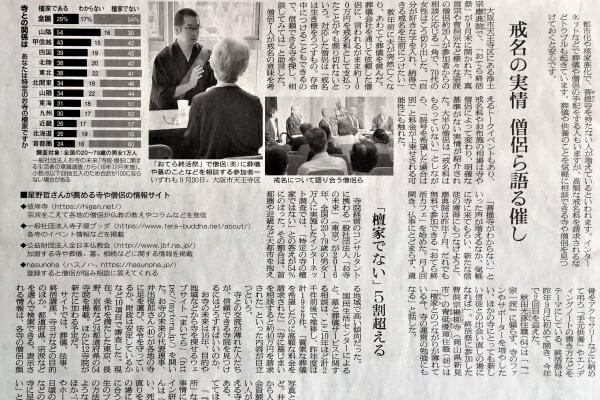


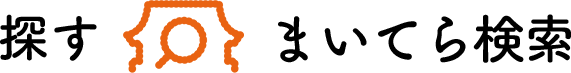

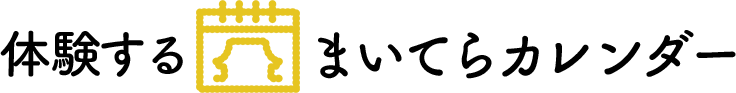
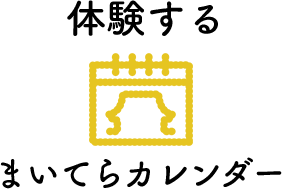
 まいてらだより
まいてらだより