もうキックバックをやめませんか ー 葬儀業界にはびこる悪しき風習(足立信行・T-sousai代表)【死に方のココロ構え(27)】
2024.06.12

足立信行(あだちしんぎょう)
株式会社 T-sousai 代表取締役社長。1982年、京都府生まれ。在家の家に生まれる。18 歳の時に高野山で僧侶になることを決意。高野山金剛峰寺布教研修生修了。高野山で修行をする中で僧侶や寺院の役割を考え、下山。葬儀の重要性に気づき、2008年 大手互助会系の葬儀会社に入社。葬儀の担当者となり、年間約 120 件の葬儀を手掛ける。2012 年IT 企業に入社し、エンジニアとして活動。2017年、僧侶と葬儀会社の担当という経験から、お互いが遺族や故人のために協力し祈りの場所として本堂などで葬儀をあげ、安価で心あるお寺葬の構想を企画。葬儀の告知、WEB、導入などから実施、施行までをワンストップできる株式会社 T-sousai を創業し、現職。
※前回(亡くなった人は「物」ではありません)はこちら
遺族の情報を売っていた市役所職員
5月に大阪府八尾市の市立斎場で斎場利用者の個人情報を提供して、その見返りとして現金を受け取っていたという事件が発覚しました。市立斎場の職員は斎場を利用した約3,000名の氏名や住所などの情報を葬儀関連商品の業者に対し、約280回にわたり書面を渡していました。斎場に勤める市立職員はもちろん、葬儀関連の業者も贈収賄の容疑で逮捕され、行政と葬祭業者との間で遺族の情報を売買されていた事実が露見しました。
少し前の2021年には、葬儀の遺体搬送を優先的に依頼するよう警察官に賄賂が送られた事件で、神奈川県の林間葬祭という企業も摘発されました。
いずれの事件も、公的な立場にある人間が金銭をもらう代わりに優先的に仕事を依頼したり情報を提供したりする、極めて悪質なものです。
こういった行政・警察と葬儀業界の癒着や贈収賄は、いまだに葬儀業界では珍しくはない側面があります。八尾市や神奈川県の事件も、数多くあるうちの一つで、氷山の一角という印象をぬぐい切れません。露見していないだけでもっと多くの案件が業界の底の方でうごめいていると考えるべきでしょう。
私自身は、このような案件が葬儀業界に根強く残る背景として、キックバックやリベートという商習慣が今日も色濃く残っていることが原因であると考えています。

葬儀業界はキックバックだらけ?
キックバックはリベートや紹介料などと呼ばれ、それ自体は商習慣として違法ではありません。様々な業界の多くの企業でなされている商慣習であり、適法であればキックバックやリベートそれ自体に問題はありません。しかし、経理上適切に処理されないものは脱法行為と見なされ厳しく処罰されます。
今回は贈収賄なのでそれ自体が違法ですが、その根底には、会社を通さない、領収書が出ない、経理上処理されない金銭の授受が当然の慣例として葬儀業界に残っていることが背景にあると考えます。つまり、キックバックや紹介料という行為が当たり前のように日常的に行われ続ける結果として、何かのきっかけで違法行為を誘発するトリガーになりうるということです。違法行為につながる可能性のある商習慣をまったく見直そうとしないのが今の葬祭業界なのです。
また優越的立場の濫用で、葬儀社に対してキックバックを要求するケースも多々あります。私自身も葬儀の営業などでいろいろな企業に足を運びましたが、「葬儀の何割かをよこせ」など、先方担当者から露骨にキックバックを要求された経験もありました。当然、領収書が出ない個人間のやり取りです。
葬儀業界はこのキックバックで成り立っている業者が少なくないと感じます。
紹介料のみで運営する葬儀社も多く、返礼品業者や生花店、仕出し業者などにキックバックを要求して葬儀社が利益を得るという葬儀社も未だ多いのが実情です。優越的立場を濫用せず、あくまでも商品やサービスそのもので判断するのであればよいのですが、残念ながらキックバックのパーセンテージで業者を決める葬儀社も多いでしょう。
しかもその結果として、キックバックの金額は、遺族の葬儀代金に跳ね返ることになります。なぜか高額な棺や高価な祭壇など、葬儀費用の不明瞭化に拍車をかけているのです。
いずれにしても、このキックバックの問題は葬儀業界全体の問題で、葬儀社が問題意識をもつべき事案です。けれどもどうしても葬儀業界単体では自浄作用は難しく限度があると思います。第三者のチェックがないと甘くなるのはやむを得ないことのように思います。
そんな中で、私は、第三者として葬儀費用などのチェック機能を、菩提寺やお寺が担えないかと思っています。要するに、葬儀費用に関するお寺によるチェックです。

葬儀の費用はお寺でチェックする
一般的に、何度も葬儀をあげる(サービスを購入する)ことは稀です。一つの家族が葬儀を出すのは多くてせいぜい2回。それ以上の回数を経験する方は少ないのではないでしょうか。むしろ、葬儀で喪主を経験されない方が圧倒的に多く、それゆえ、葬儀費用に対する適切な目線が消費者側に育まれにくい構造があります。
「父の時はこうだった」「母の時はこうだった」など、家族間での何年も前の記憶をもとに検討されるため最新の情報が更新されず、葬儀社の言うがまま、なすがままというケースがほとんどです。これでは見積もりも請求も、そしてキックバックも甘くなるのは当然なのかもしれません。
それをチェックするためには第三者の、葬儀に慣れた、客観的な人物が観るのが最も適しています。それができるのは、お寺や僧侶しかいないように感じるのです。
葬儀社を何社か周り、見積書を比べてみるのもいいのですが、葬儀社の見積書は各社同じようなフォーマットがあるわけでなく、商品構成やコース(プラン)も多岐にわたるため、比較ができるようでなかなか難しいのが実情です。そんな時にお寺に相談し、見積書をチェックしてもらい、本当に適正な価格の見積もりなのかをチェックしてもらう。これが新しい葬儀のスタイルなのではないでしょうか。
チェック機能をしっかりすることで葬儀社のぼったくりもなくなりますし、病院や警察などへのキックバックの跳ね返りも見極めることができます。今こそ、お寺が求められる時代なのではないでしょうか。
そして、最後に葬儀業界に携わる方々。もうキックバックをいい加減、やめにしませんか?

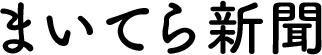

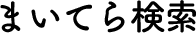

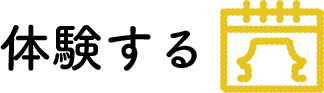
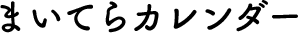
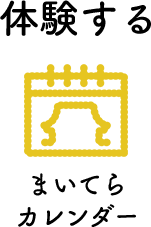

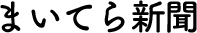

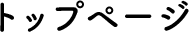
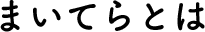
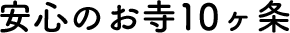
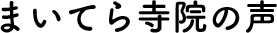
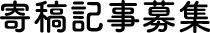
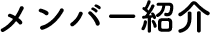
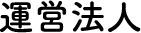



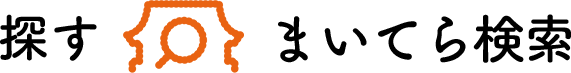

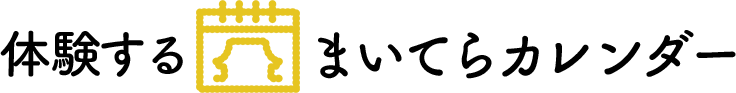
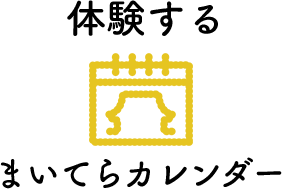
 まいてらだより
まいてらだより
東北 関東北部でいま冠婚葬祭の幅を広げてるs典礼に 地元にあった葬祭店が乗っ取られたか買収されました。そこを介して仕出ししてた私の飲食店は買収まえのリベートは5%でした買収され10%に上げられました。まぁ地域のほかの飲食店もその位だからしょうがないなと渡してましたが半年後次回からリベート30%にすると一方的にきめられました。いやいや飲食店は10%も利益率ないしこの食品や人件費、光熱費の値上げで無理です。せめて一年間10%やって
一年後5%ずつあげるのなら納得できますといいましたが聞く耳もたず。今まで7000円の料理の700円リベートが2100円取られたらお客さんに出すのは4900円そこから500円利益とるなら実質4400えんの作らないと無理。お客さんは7000円払ってこれだけ?になるしこっちの評判わるくなるし最悪です。困った業者です。