かなしみを超えて、つながりへ ― 玉蔵院が育むグリーフケアの場(玉蔵院住職・本多法仁)
2025.10.28
大切な人を失った悲しみは消えることはありません。しかし、その悲しみを共有し、語り合える場があれば、心は少しずつ和らいでいきます。
玉蔵院の「グリーフケアのつどい」は、悲しみを超えて人と人をつなぎ直す取り組みです。その歩みと、場から生まれる変化や学びについて、玉蔵院住職の本多法仁さんにつづっていただきました。

本多法仁(ほんだほうじん)
鎌倉学園高等学校を卒業後、高野山専修学院にて1年間の修行を成満。法政大学経済学部卒業後、旅行会社に勤めながら未来の住職塾を受講。退職後、そのご縁で1年間ほど(一社)お寺の未来に勤務。その後、自坊に戻り、日々勉強中。
悲しみや様々な気持ちを分かち合う場

玉蔵院では春と秋のお彼岸の最終日に「グリーフケアのつどい」を開催しています。
グリーフとは「深い悲しみや喪失感」を意味し、具体的にはご家族をはじめとした大切な人や健康や普段の日常生活などを失う事によって生じる、その人なりの自然な反応・状態・プロセスを指します。(一般社団法人リヴオンHPより)
グリーフケアのつどいでは、グリーフそのものを解決するというよりも、なかなかご家族やご友人にも言いにくい感情を共有する場としております。お一人おひとりが安心して気持ちを吐露できるように、話し合われたことはその場に置いてお帰りいただきます。
プログラムとしては、本堂にて参加者それぞれの大切な存在を思い浮かべながらお経を唱え、瞑想し、ゆったりと気持ちを落ち着けた後に分かち合いの時間に移ります。発言は強制ではなく、話したくなった人からお話しいただきます。全体で2時間くらいですが、毎回あっという間に時間が過ぎていきます。
転機となった気づき
玉蔵院のグリーフケアのつどいは2020年に初めて開催しました。以降、春と秋のお彼岸に開催し、2025年の秋彼岸で10回目を迎えました。
実は私自身、第4回までは毎回戦々恐々としておりました。
その一番の理由はつどいに参加していただいた方を、私の不用意な発言でひどく傷つけてしまうかもしれないと、必要以上に思い詰めていたことが原因でした。
ただ、第5回を開催した時に転機がありました。
「それぞれの悲しみを持ち寄る場ではあるけれども、悲しみが参加者の全てではない。悲しみは、目の前にいらっしゃる方を構成している一部に過ぎないのではないか」
ふとこのように感じたことで気持ちが楽になり、場を運営する私の懐が一気に広がった気がしました。
そんな私の思いが伝染したのか、それ以降にポジティブな変化が生まれました。
例えば、つどいに何度も参加されている女性が、同じ病気で旦那様を亡くされた方を個人的に集めてお茶会を定期開催したり、LINEグループを作って誰かが気が滅入っている際には電話でその方の話を聞いてあげる関係性を構築されています。
また他の事例では、奥様を亡くされた参加者の男性はふとしたきっかけで誘われた民生委員を担い、その活動の中で様々な理由で独居になってしまった方と、ご自身の死別体験をお話ししながら関係を育み、地域のセーフティネット的な存在になられていたりと、うれしい連鎖が生まれています。
悲しみを持ち寄るだけの場だったつどいが、今では近況報告の場となり、そして参加者とそれぞれが亡くされた大切な方を確かに感じることのできる、包容力のある場となっています。
悲しみからつながりへ
場が変化しても、今でも「何年経っても悲しみは無くならない」とみなさんが口をそろえてお話しされます。
抱える悲しみとともに長く歩んでいくからこそ、自分自身を保つために「自分がご機嫌でいられる何かを見つける事の重要性」、そして「気持ちが落ち込んでいる時に話を聞いてもらえる相手の大切さ」について、つどいに参加されている方々から私自身も教わっています。
きっと誰しもが何かしらの悲しみや辛さを抱えながら生きています。時にはやり切れない事もあるでしょう。
そんな時にその思いを分かち合えるお寺としてありたいと強く思います。玉蔵院につどうみなさんにとって、いつの日か「かなしみ」が「つながり」のご縁を導いたと感じられますよう願いを込めて。

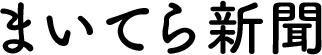

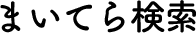

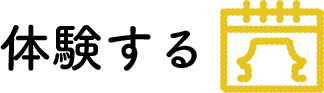
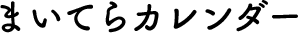
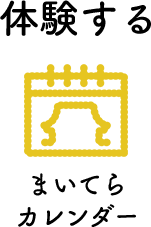

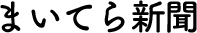

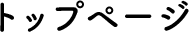
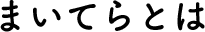
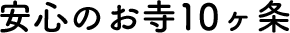
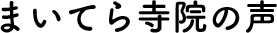
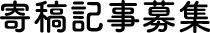
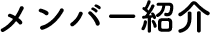
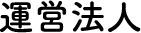

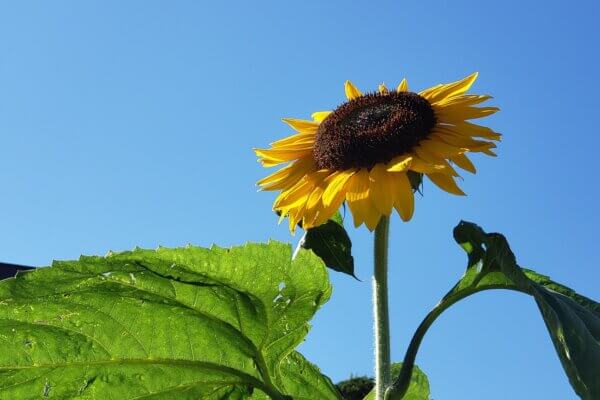

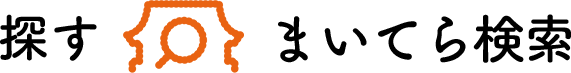

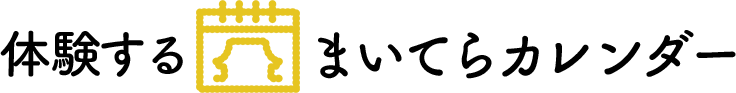
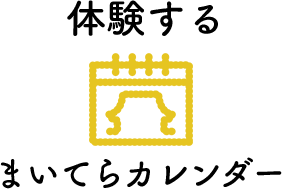
 まいてらだより
まいてらだより