400年の祈りを未来へ ― 藤堂高虎公供養祭(四天王寺住職・倉島隆行)
2025.10.21
三重県は津の町を築いた戦国武将・藤堂高虎公を偲び、初めて神職と僧侶がともに営んだ合同供養祭。多くの市民が集い、甲冑姿の奉納演武や、読経・祝詞が交わされ、雨予報を吹き飛ばす晴れ間の中、祈りは未来へとつながっていきました。当日の様子を四天王寺・倉島隆行住職が語ります。

倉島隆行(くらしまりゅうぎょう)
大本山永平寺で修行後、欧州等へ参禅修行に向かう。その後、伊勢皇學館大学に結集された伊勢国際宗教フォーラム世話人としてダライ・ラマ14世を招聘するなど、様々な宗教の垣根を超えて諸宗教対話に尽力している。
※関連記事(津の恩人・藤堂高虎公に感謝し、丁寧なご供養を捧げたい)はこちら
藤堂高虎公を墓前で偲ぶ、初めての神仏合同の供養祭

津の町を築いた戦国武将・藤堂高虎公。その功績を偲ぶ供養祭が10月5日(日)に初めて神職と僧侶が合同で営む形で行われました。
津市にある寒松院の墓前に到着してまず驚いたのは、甲冑姿で奉納演武をされた方々やメディアの取材も含めてすでに40名が集まり、お祭りのような雰囲気だったことです。普段は淋しい雰囲気の墓地ですが、その日は人の温もりと熱気が満ちていました。
今までの年は五日会という有志団体が掃除とお参りを行う程度で、僧侶や神職が加わることはなかったそうです。だからこそ、今回の読経や祝詞は、参加者の心に深く響いたようです。実際、涙を流された方もおられました。
式次第は神仏合同の形で進められました。まずは藤堂高虎公を祀る高山神社の多田宮司が祝詞を奏上し、地域・土地への感謝と藤堂高虎公の功績を言霊に託しました。
印象的だったのは、高虎公によって津の町が形づくられたわけですが、津という土地への感謝が込められていて、非常にスケール感の大きな祈りだったことです。仏教の供養が個人に焦点を当てるのに対し、神道は空間や自然を含めて広く感謝するという、その対比がとても心に残りました。

続いて私を中心に、曹洞宗・臨済宗・浄土真宗の有志僧侶が読経を行い、その後に参列者一人ひとりが焼香しました。思いのほか丁寧に焼香される方が多く、読経は五巡しました。みなさんの高虎公への感謝の祈りが強く表れたのだと思います。
最後に私が回向文を読み上げ、高虎公を偲び功徳をめぐらせて、式を締めくくりました。


当日は雨予報が続いていましたが、儀式の間だけ奇跡的に晴れ間が差したことも印象深い出来事でした。神仏や高虎公に見守られているとしか思えない天気でした。終わって一時間ほどで豪雨になったのですから。

深い祈りを通じ、お寺の縁起を身体で理解できた
今回の供養祭を通じて、私自身も様々な気づきをいただきました。
当初は近しい人たちだけで静かに墓前法要を勤めようと考えていました。しかし、市民や議員、そして藤堂家の末裔の方々まで思いを寄せてくださり、高虎公が礎を築かれた郷土への愛は多くの人をつなぐ力があるのだと感じさせられました。郷土愛を共通の気持ちとして人々が集い、僧俗ともに祈りを捧げられたことが大きな意義だったと思います。
そして、私がお預かりしている四天王寺は、400年前に藤堂高虎公に再建いただいた歴史があるのですが、今回の供養祭を通じてその歴史を体感できたことも心に残りました。その歴史的事実は文献を通じて知識として理解していましたが、実際に深く祈りこむことで、400年前のお寺の縁起を身体で感じられたのです。変化が速い世の中では、未来にばかり目が向きがちですが、過去に向き合うことで四天王寺の縁起を実感できたのは大きな収穫でした。
2030年は400年大遠忌
翌朝、高虎公の正室・久芳院のお墓にお参りし、供養祭が無事に執り行われたことをご報告しました。前日の余韻さめやらぬ中、お参りされたみなさんの温もりをそのままお供えしたいと手を合わせたところ、温かい光が墓石に宿るように伝わってきました。喜んでいただけたのではないかと、住職として胸をなでおろしました。

実は、火事によって久芳院のお位牌は現在の四天王寺には存在していません。しかし、今回を節目に、お位牌をしっかりお祀りしようと決めました。高虎公のご分祀も整え、ご夫妻をご一緒に祀らせていただきたいと思っています。
2030年には藤堂高虎公の没後400年の節目を迎えます。高虎公をご縁とした郷土愛を持つ多くの人が集う、素晴らしい400年大遠忌を迎えられるよう、来年以降も丁寧に供養祭を営みたいと思います。高虎公を偲ぶ祈りは、これからも津の町をつなぎ、未来を照らし続けていくでしょう。


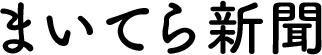

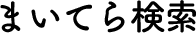

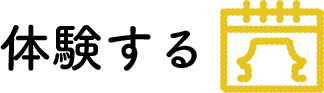
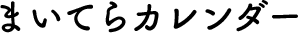
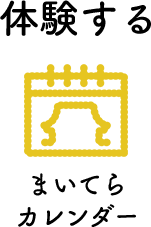

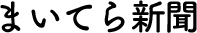

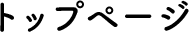
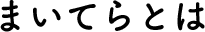
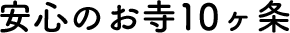
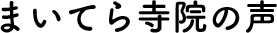
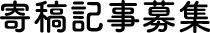
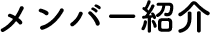
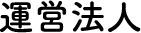


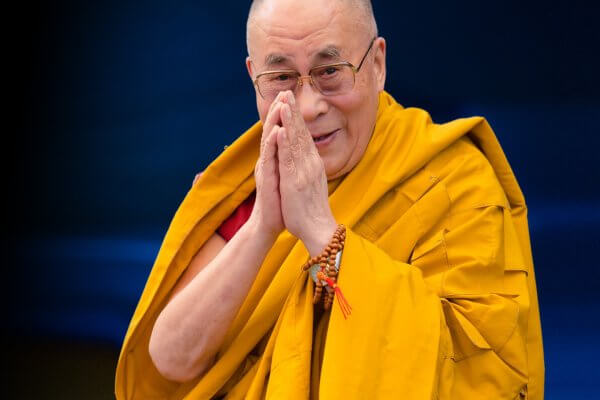
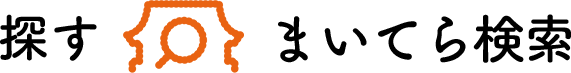

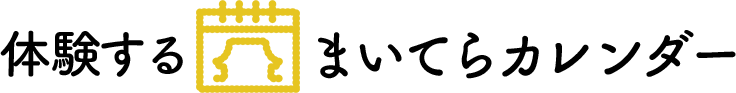
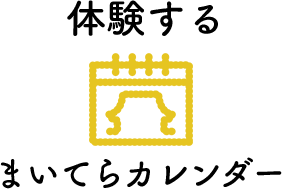
 まいてらだより
まいてらだより