【藤田一照さん(僧侶)の“いのち”観/後編】- 人は死後「かたちのないいのち」に帰っていく –
2017.08.01

禅僧・藤田一照さんの“いのち”観インタビュー。前編の「他者は死んだらどうなると思いますか?」に引き続き、後編は「自分は死んだらどうなると思いますか?」という質問からスタートしました。最後までおたのしみいただけますとさいわいです!
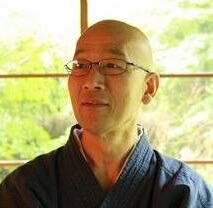
藤田一照(ふじた・いっしょう)
1954年、愛媛県生まれ。灘高校から東京大学教育学部教育心理学科を経て、大学院で発達心理学を専攻。院生時代に坐禅に出会い深く傾倒。28歳で博士課程を中退し禅道場に入山、29歳で得度。33歳で渡米。以来17年半にわたってマサチューセッツ州ヴァレー禅堂で坐禅を指導する。2005年に帰国し、現在、神奈川県葉山の「茅山荘」を中心に坐禅の参究、指導にあたっている。曹洞宗国際センター所長。
死は決して体験できないし、知ることもできない
――では、続いて、第一人称の死、つまり自分自身の死について、「人は死んだらどうなると思いますか?」という質問にお答えいただけますでしょうか。
第一人称的に言うのなら、「死」はないですね。
――「死はない」ですか!
ない、というと言い過ぎかもしれないけれど、少なくとも、僕自身は、僕の死を目撃できないですよね。「俺が死ぬところを見たぞ!」って言っている人がいたら、その人は生きているということになりますから(笑)。
――確かにその通りですね。
死って、第一人称の「私」には、決してタッチできないものなんですよ。自分の死に触れることはできないし、知ることもできない。体験ができないわけですからね。だから、僕らが自分の死についてできる最大限のことは、死というもののわからなさ、不可知さを細かく思索して、「わからない」ものを「わからない」ままに実感に落とし込んでいく、ということになるでしょうね。
――無理やり「わかる」ものに変えてしまわずに。
そういうことですね。自分の生の最後に、どうしたって自分の頭で考えて知ることのできない「死」という領域が控えている、そういう「生」を生きているということをそのまま受け取って、きちんと吟味して、深く理解していくと、日々の選択の仕方とか、物事の感じ方とかがおのずと変わっていくと思うんですよ。そうすると「生」に立体感が出てくる。生きる実感みたいなのも、そこから湧き上がってくるんじゃないですかね。
――まさしく、この連載タイトル「死を想って生きる」ということですね。
本来的ないのちにははじまりも終わりもない
もうひとつ、別の角度から「人は死んだらどうなると思いますか?」という質問に答えるとしたら、「ふるさとに帰る」という言い方ができると思いますね。
――「ふるさと」ですか?
元の場所、ということですね。曹洞宗では、亡くなった方の位牌に「新帰元(しんきげん)」という言葉を付けるんです。「新帰元〇〇居士」みたいな風に。死んだ人はどこかに飛び去ったわけではなくて、元の場所に帰ったんだ、と。元の、かたちのないいのちに帰っていったんだ、ということですね。
――かたちのないいのち。
かたちのない、無限のいのち。それが背後にあって、はじめて、決まったかたちをもった、有限のいのちがあらわれてくるわけで。本来的ないのちには、そもそもはじまりも終わりもないんですよ。そちらの方に自分をアイデンティファイしていれば、やっぱり、死はない、ということになりますよね。
――いのちにはじまりもなく終わりもないのならば、そもそもなにも生まれないし、それゆえになにも死なない、ということになりますものね。
そう。だから、「生まれたり死んだりしないいのちを、生まれたり死んだりする私が生きている」という風に言えばいいかな。いや、「生まれたり死んだりしないいのちが、生まれたり死んだりする私を生きている」と言った方が正確かな……。なんだかややこしいけれどね(笑)。そこに絶対的な安心というのが生まれてくるんじゃないですかね。僕はそう思っています。
――藤田さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。
※こちらの連載はTemple Webとの連動企画です。「藤田一照さんとの対話/かたちなきいのちに「触れられた」瞬間」もあわせておたのしみくださいませ!
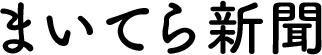

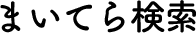

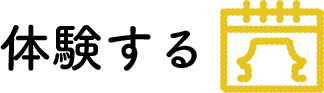
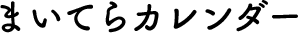
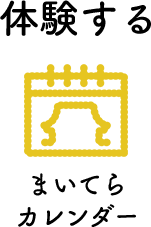

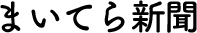

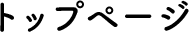

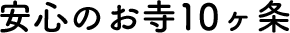
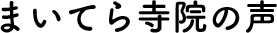
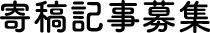
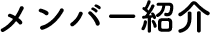
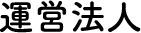



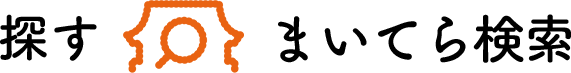

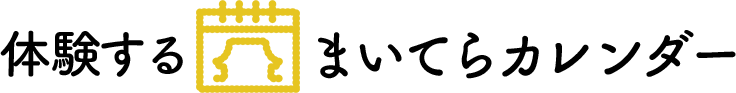
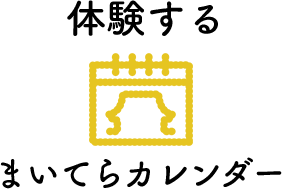
 まいてらだより
まいてらだより